「単体では機能しても、組み合わせたら急に勝率が落ちた…」
バイナリーでありがちな失敗の多くは、インジケーターの“相性”と“役割の分担”を理解していないことにあります。
本記事では、実際の裁量トレーダーの視点から見て
**「相性が良く、バイナリーで勝率を高めやすい」**インジケーターの組み合わせを10個厳選しました。
💡 実際にBubingaで使用可能なインジを中心に構成しており、
初心者〜中級者が「迷わず再現しやすい構成」にしています。
インジケーターは“組み合わせてこそ意味がある”
💡 用語に迷ったらこちら!

インジケーターやローソク足の意味がわからない場合は、検索でジャンプできます🔍
「RSIだけでエントリーしてるけど勝率が安定しない」
「MACDのゴールデンクロスで入ったのに、逆行した…」
そんな失敗は、インジケーターの“組み合わせ不足”が原因かもしれません。
🔍 単体では“弱い根拠”になりやすい
インジケーターはそれぞれ役割が違います。
| 種類 | 役割 | 代表インジ |
|---|---|---|
| トレンド系 | 流れや方向性を判断 | SMA / EMA / GMMA / TEMA |
| オシレーター系 | 買われすぎ・売られすぎ判断 | RSI / CCI / ストキャス |
| ボラティリティ系 | 勢いや荒れ具合を確認 | ATR / ADX |
| 補助系 | ノイズ除去や平滑化 | DEMA / HMA / エンベロープ |
それらを**“1つだけ”で使うと視点が偏り、だましに弱くなる**のです。
組み合わせを選ぶ3つの基準
インジケーターを適当に組み合わせても、勝率が上がるわけではありません。
むしろ、似たような性質のインジを重ねすぎて根拠がブレるのがよくある失敗です。
ここでは、プロ視点で見た「組み合わせ選定の3つの基準」を解説します。
① 役割がかぶっていないか?【補完関係を意識】
| ダメな例 | 原因 |
|---|---|
| SMA × EMA × TEMA | すべてトレンドの“滑らかさ”を示す系 → 見解が似すぎて意味がない |
| RSI × CCI × ストキャス | 全部オシレーター系 → タイミング判断しかできない |
✅ → 「方向を見る」「タイミングを測る」「勢いを確認する」など役割を分けるのが鉄則です。
② 地合い or タイミング、どちらを見たいのかを明確に
- 「今はエントリーすべきか?」:ストキャスやRCIなどの短期系
- 「今の相場は買い場?売り場?」:TEMAやGMMAなどで環境認識
💡 これを明確にしないと、“どこを見ていいか分からないチャート”になります。
③ 自分のスタイルに合った視認性・反応速度を選ぶ
- スキャル系(秒〜1分足) → 反応が速く視覚的なものが有効(HMA、ストキャスなど)
- じっくり見て判断するタイプ → 地合い重視(GMMAやKAMA)
✅ 一番大事なのは「自分が読んで迷わないチャート」であること。
【TOP10】勝率を上げるインジケーター組み合わせランキング
ここからは、プロ視点で実戦的に使える組み合わせTOP10を紹介していきます。
すべてBubingaで表示可能なインジケーターのみで構成されており、初心者でも再現しやすいのが特徴です。
第10位|SMA × RSI:シンプル&王道の逆張り基本形
- SMA:全体のトレンド方向を確認
- RSI:買われすぎ・売られすぎの目安でエントリータイミングを計る
🟢 おすすめポイント:とにかくシンプル。初心者でも視認しやすく、王道パターンの練習に向く
🔴 注意点:逆張り限定。強いトレンドには弱く、“だまし”を受けやすい
第9位|EMA × CCI:滑らかにトレンド追従+水準判断
- EMA:方向性・勢いを捉えるトレンドフォロー型
- CCI:0ラインからの乖離で逆張り水準も狙える
🟢 EMAの角度とCCIの跳ね返りを組み合わせることで、押し目や戻りからのエントリーがしやすい
🔴 トレンドがはっきりしないレンジでは誤爆も
第8位|TEMA × ストキャス:地合いの流れ+タイミングを両立
TEMA:ノイズを抑えながら反応も速い、滑らかなトレンドライン
ストキャス:エントリーの細かいタイミング把握
🟢 短期足でも“だまし”を減らし、トレンド転換の見極めに強い構成
🔴 ストキャスの過信はNG。補助的に使い、背景の流れはTEMAで確認
第7位|GMMA × RSI:長短の流れで地合い把握+逆張り判断
- GMMA:長期と短期の移動平均を束ねた「地合いの地図」
- RSI:高値圏・安値圏での逆張りポイントを探す
🟢 GMMAで「買い場か売り場か」を判断し、RSIで“タイミング”を取る構成
🔴 GMMAは初見だとやや見づらいので、慣れが必要
第6位|エンベロープ × RCI:逆張りに強いバンド戦略
- エンベロープ:一定幅の上下バンドで反転を視覚化
- RCI:時間軸の相関から反発の確度をチェック
🟢 両方とも“逆張りの補強”に強く、ローソク足と合わせれば根拠が重なる
🔴 トレンドが強すぎると、エンベロープは機能しにくい
第5位|ATR × CCI:勢い+逆張り判断のハイブリッド
- ATR(平均的な値動きの大きさ):相場の勢い・荒れ具合を数値化
- CCI:水準的な反発可能性を判断
🟢 ATRで“今エントリーしても間に合うか”の判断、CCIで“反転するタイミング”の判断
🔴 ATRはあくまで補助。エントリーの直接根拠にはしない
第4位|ADX × ROC:トレンドの強さ × 勢いの加速をセットで把握
- ADX:トレンドの有無と強さを数値で確認
- ROC(変化率):勢い・加速の判断
🟢 「今のトレンドが本物か?」という環境認識+押し目拾いに特化
🔴 どちらも「判断材料」寄りなので、単体判断には向かない
第3位|MACD × ストキャス:ゴールデンクロス+タイミングの王道セット
- MACD:方向性+クロスでの転換判断
- ストキャス:エントリーの細かいタイミングを狙う
🟢 MACDのクロスで方向を掴み、ストキャスでタイミングと反発を可視化
🔴 ストキャスの“動き過ぎ”に要注意。MACD優先で補助的に使う
第2位|GMMA × RCI:相場の地合い+反発ポイントを一括把握
- GMMA:短期〜長期の重なりから、トレンドの“勢い”や“転換”を視覚化
- RCI:時間軸ごとの相関を見て、タイミングを探る
🟢 トレンド&逆張りの**“ミックス戦略”**にぴったり!中級者〜上級者向け構成
🔴 チャートがやや複雑になるので、色やラインの工夫が必要
第1位|TEMA × CCI:滑らかなトレンド判断+反発の信頼度が高い
TEMA:ノイズを抑えながらも反応が速く、トレンド方向をなめらかに示すインジケーター
CCI:価格の平均乖離を視覚化し、反発タイミングを計れる水準系オシレーター
🟢 方向性をTEMAで読み、CCIで反発を拾うという“順張り×逆張り”の王道構成。
視認性が高く、再現性も安定しており、初心者にも扱いやすいペアです。
🔴 CCIが難しければ、RCIやストキャスでも応用可能!
やってはいけない組み合わせ例とその理由
どんなに優れたインジケーターでも、“相性が悪い” or “意味が重複する” 組み合わせで使うと、
判断を迷わせてしまい、むしろ勝率が下がる原因になります。
ここでは、実際によくあるNG構成とその理由を紹介します。
❌【NG例1】SMA × EMA × TEMA
→ 全部「トレンドの滑らかさ」を見る指標。
結論が似すぎて「違いが読めない」=判断に迷う
✅ どれか1本にして、補助やオシレーター系と組み合わせるのが正解
❌【NG例2】RSI × ストキャス × RCI
→ すべてオシレーター系。
「全部売られすぎなのに上がらない…」など、根拠が重なりすぎて逆に読めなくなる
✅ タイミング系は1つに絞って、地合いや勢いを見る補助指標を加える方が精度UP
❌【NG例3】MACD × GMMA(+移動平均3本)
→ 方向性・クロス・流れ・角度…すべて似たことを別の形で伝えてくる
→ 結果的に「何が強い根拠か分からない」
✅ 視認性を犠牲にせず、“判断の軸”を絞ることが大切
💬 結論:情報が多すぎると「迷い」が増える
インジケーターの“複数使い”が効果を出すのは、
あくまで「それぞれが異なる視点を補い合っているとき」です。
実際に使うなら?Bubingaで環境を再現する方法
「理想の組み合わせは分かったけど、実際にそれを使える環境ってあるの?」
そんな疑問に対して、実はBubinga(ブビンガ)がまさにピッタリの環境です。
✅ Bubingaなら、組み合わせ自由・カスタマイズも直感的
- ✅ 主要な移動平均線(SMA/EMA/TEMA)
- ✅ 豊富なオシレーター系(RSI/RCI/CCI/ストキャス)
- ✅ ボラティリティ・補助系(ATR/ADX/エンベロープ など)
これらがスマホ1つで切り替え可能なチャートUIで搭載されています。
🔍 実際に記事内で紹介した組み合わせは、すべてBubinga上で表示可能です!
🚀 Bubingaで今すぐ試してみる
- 📱 スマホ対応でスムーズ
- 🧭 自分好みにインジ配置を調整可能
- 💡 登録時に【ORIKEN50】を入力すれば初回入金ボーナスあり
まとめ|戦略的に組み合わせて精度の高いエントリーを
インジケーターは単体では見えないものを補い合うことで、本当の力を発揮します。
本記事で紹介した10の組み合わせは、すべて実践で再現可能で、
**「トレンド判断 × タイミング × 地合い補足」**のバランスが取れた構成です。
✅ 覚えておきたいポイント3つ
1️⃣ “役割が異なるインジケーター”を掛け合わせることが大原則
2️⃣ 自分のトレードスタイルに合った視認性・反応速度を選ぶこと
3️⃣ 環境認識・補助・タイミング判断を分けて考えるのが勝率UPの近道
📚 関連記事もチェック!

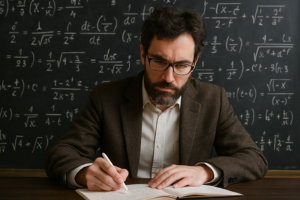










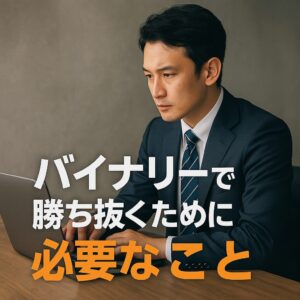


コメント